
-MENU-
いま一番多い中3生のクラスが18名である。
大体、十数名のクラスで、小学生のクラスは10名に満たない。
塾の規模としては小規模に属するだろう。
保護者の方々が心配される通り、講師一人あたりの生徒数は、面倒見の良さと密接に関係している。
生徒と進路や勉強に関する面談をする
分からないところの質問対応をする
授業中に回答・発言してもらう
小テストの内容を精査する
一人一人の勉強の内容(勉強の仕方)を指導する
ちょっとしたことでコミュニケーションを取る
こういった場面において、一人一人にかけることができる時間が多いほど、
塾生たちを手厚くフォローすることができるのは紛れもない事実だ。
前職でも経験しているが、生徒数があまりにも多すぎると上記のようなフォローがどうしても渋滞、遅延しがちである。
どうしても妥協せざるを得ない場面が出てくる。
また、生徒に関してだけでなく、保護者の方々へのフォロー、コミュニケーションに関しても同様である。
塾生の保護者の方々と面談をさせていただくときも、

最近、生徒さんがだいぶ増えたみたいですね。
と仰っていただくことがあるが、なんとなく申し訳ない気持ちになる。
「もしかしたら、生徒が増えることで一人ひとりへのフォローが弱くなってしまう」
「疎かになってしまうとご心配をおかけしてしまっているかもしれないな。」と思うからだ。
ただ、unitでは生徒一人一人のことをじっくりと見ることを大切にしているし、
この点に関しては今後も全くぶれることのない指針である。
この点、保護者の方々にはご安心いただきたい。
ちなみに、私が懇意にさせていただいている塾の先生方には個人塾でありながら多くの生徒さんを指導され、
尚かつきめ細やかで熱量の高い指導をされていらっしゃる先生方もいる。
私もいずれはそういう高い次元での指導ができるようになりたいと思っているが・・・、まだまだ修行が足りない。
塾では自習室の利用を推奨している。
中3生は授業の時間帯よりもだいぶ早くから塾に来て(だいたい16:30過ぎ)黙々と勉強しているし、
授業後も22:30くらいまで勉強している。
週6で塾に来る子が大半だ。
また中2の子たちも週に4,5回ほど塾に来るのが通常運転となっている。
最近は小学生の子たちも授業以外の曜日に自習に来る。塾の宿題や学校の宿題にせっせと取り組んでいる。
塾生たちが自習に来たとき、私たちは授業をしながら、一方で塾生たちの勉強の様子を見る。
何の教科を勉強しているのか。
正答率がどのくらいか。
丸つけが丁寧に行えているか。
字が丁寧か。
間違えた問題の修正がきちんとできているか。
集中して勉強に取り組むことができているか。
勉強しているときの姿勢や表情はどうか。
いろいろなことを見て、気づいたことや助言などがあればその都度声をかける。
まだ質問する習慣がついていない子、間違えた問題の修正がまだ定着していない子、苦手教科を勉強している子には
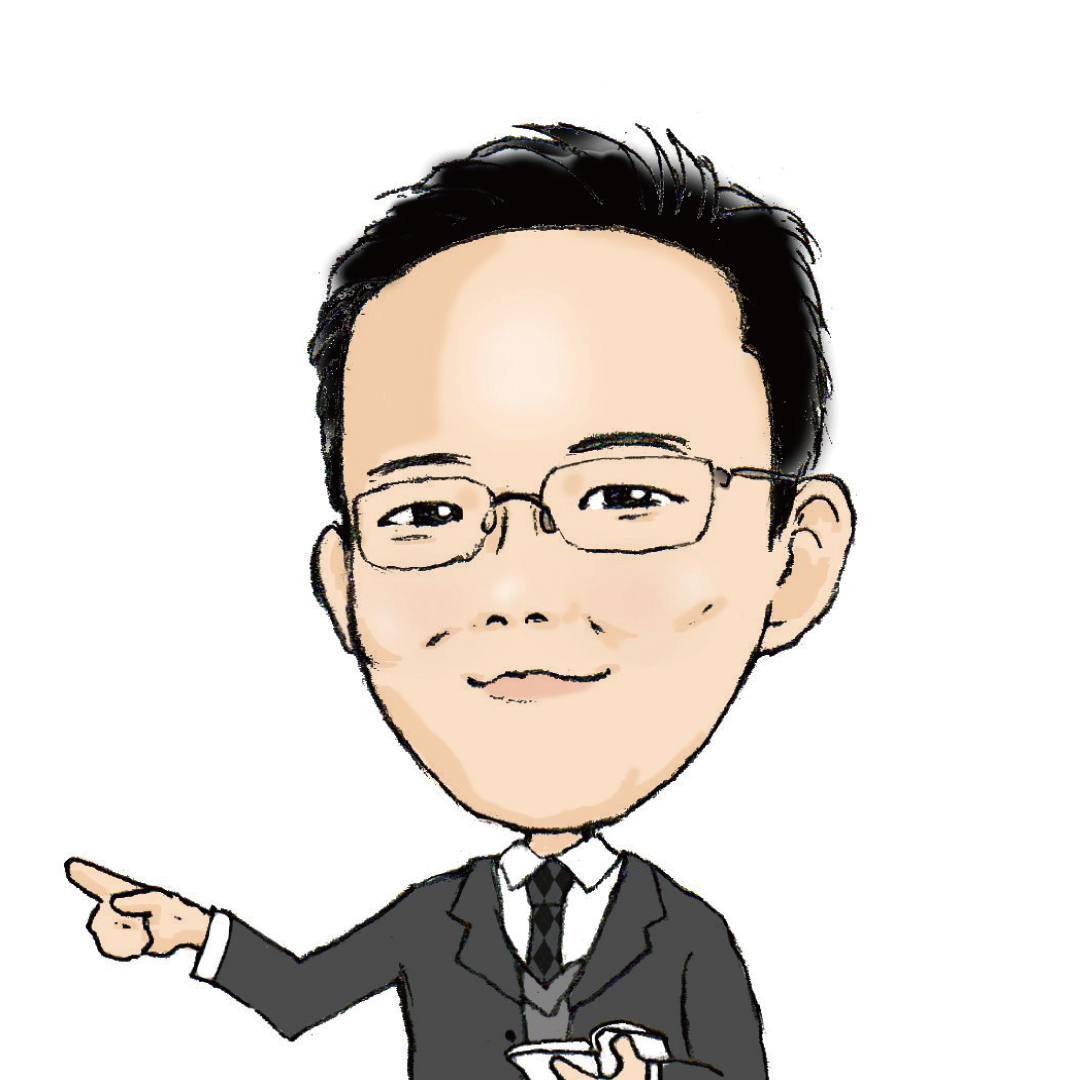
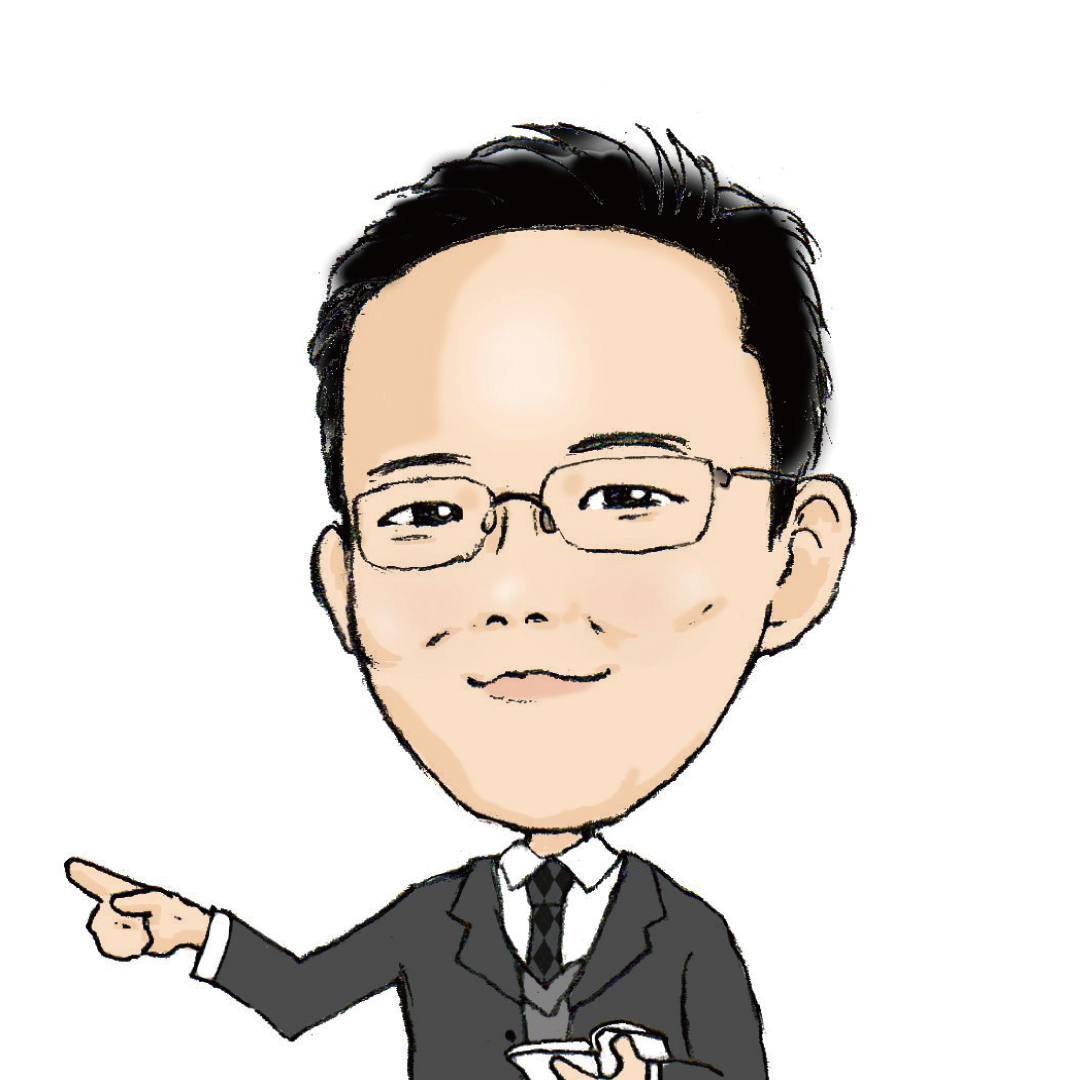
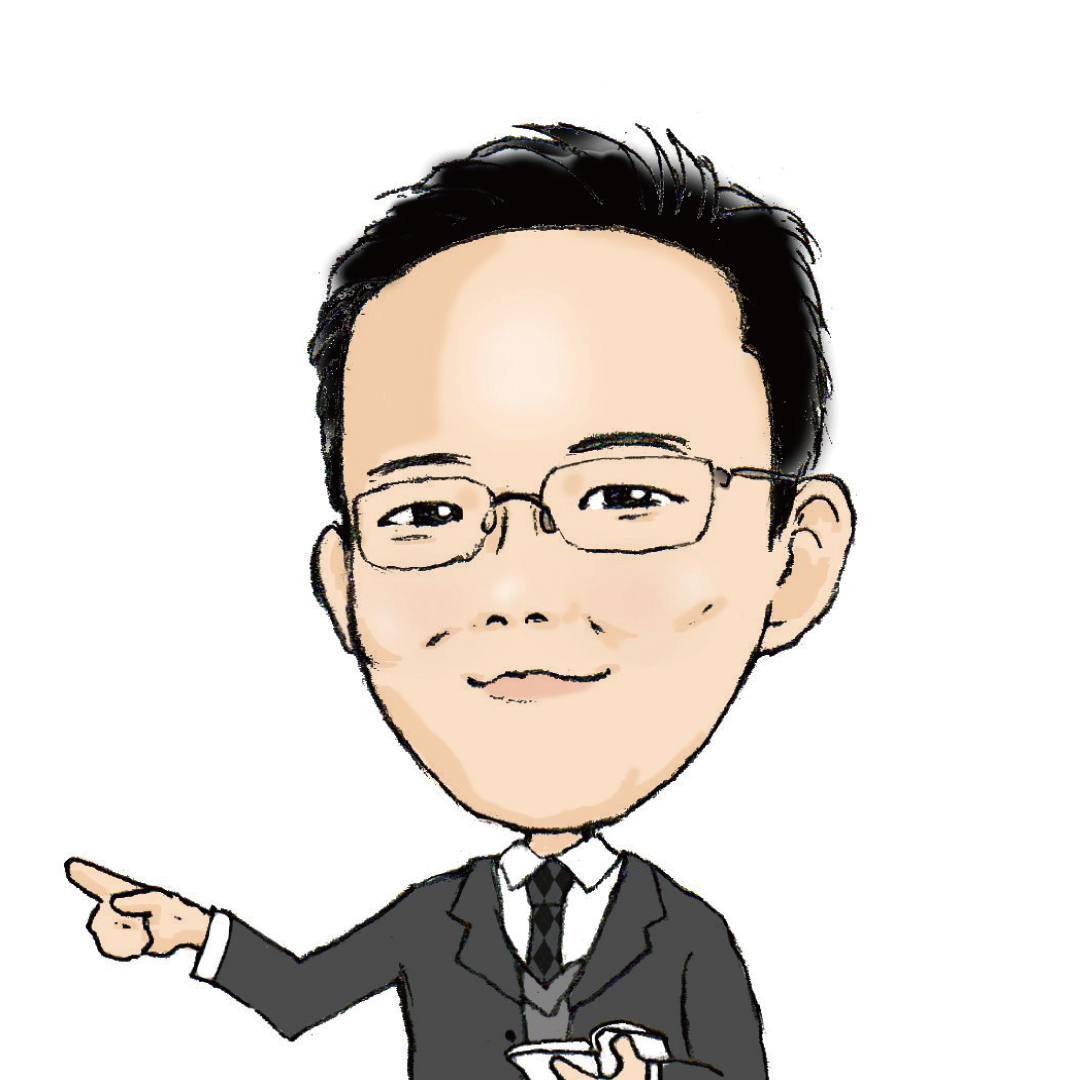
分からないところがあったら遠慮なく持って来なよ。今のところ、何か聞いておきたいことはあるかい?
と声をかける。
すると、おもむろにワークやプリントを出してきて、「ここがよく分からないです。」と質問してくれることもある。
「家で勉強しているときよりも、より質の高い勉強ができるように」ということを意識している。
ところで、たまに入塾面談のときに他塾のお話をしてくださることがある。
「以前に通っていた塾でも自習をしに行っていたのですが、
他の子のおしゃべりの声がうるさくて集中できない、と帰ってくることがありまして・・・」みたいなお話を聞く。
どの程度のおしゃべりなのか、頻度はどれくらいなのか。
実際のところは直接見ているわけではないので何とも言えないが、そのようなお話が出てくること自体、非常に残念である。
塾がどういう場所か、自分のために、周りの子のためにどのように振る舞うべきか。
そういうことは指導者が生徒たちに繰り返し説いて、価値観・意識の共有を図っていかなければならないことである。
中にははじめから備わっている子もいるが、様々なやりとりを通じて指導者が積極的に意思の疎通をはかるべきである。
一事が万事。
そういう指導がしっかりと成されているからこそ、
勉強の仕方やその他諸々についてもちゃんとした指導ができると私は思う。
自習ができる塾はたくさんあるかもしれないが、
集中して自習できる塾となると、もしかしたら意外と少ないのかもしれない。
真面目にやろうとしている子にとって居心地の良い空間づくりを心が
仲の良いお友達と一緒に通うことに対して、少し不安を覚える保護者の方もいらっしゃるようだ。



仲が良いのは良いことだけれど、授業や勉強に集中できないのでは…。



授業中や自習中にしゃべってしまったりしないだろうか…。
という不安があるのだと思う。
進学塾unitでは、勉強する時間とそうでない時間のメリハリを大切にしている。
授業中、自習中はみんな集中して黙々と勉強に取り組む。
休み時間は友だち同士でしゃべったり、先生たちとしゃべったり、マンガを読んだり、にぎやかに過ごしている。
休み時間が終わるチャイムが鳴ると、ピタッと静寂が訪れて、再びそれぞれが勉強モードに入る。
仮にその中でいつまでもペチャクチャおしゃべりをしている子たちがいたら、ものすごく目立つと思う。
お互いに仲良く話せる間柄でありながら、お互いが刺激し合い切磋琢磨する。
しんどいときには、お互いに励まし合う。
実際にそういう関係が塾生同士の間でたくさん見られる。
仲の良い子と一緒に勉強することのマイナス面(依存、足の引っ張り合い)が非常に出にくく、プラス面が出やすい環境だと思う。
私自身、友人や仲間と過ごすときに、一緒にいる時間が充実したものになる関係、お互い成長できる関係を大切にしてきたように思う。
塾生たちにもそのような関係を築いていってもらいたい。
新しい環境に入っていくとき、そこにいる人たちとうまくやっていけるか、というのは大なり小なり気になるところだと思う。
手前味噌な話になるが、進学塾unitの塾生は新しく入ってくる子たちに対して、かなりウェルカムな雰囲気で接してくれていると思う。
自分たちから明るく挨拶をして、積極的にコミュニケーションを取ってくれる。
塾生たちも自然体だし、入ってきた子も自然体で過ごしやすいと思う。
厄介なのが、もともとその集団の中にある特定の「グループ」ができている場合だ。
ここで言う「グループ」とは内輪のノリが強い集団、排他的な雰囲気の集団である。
「○○中の子たちのグループ」とか「特定の女の子たちのグループ」とかそういうものが出来やすい。
しかし、unitは異なる中学校に通っている子たちのあいだの垣根や、男子と女子のあいだの垣根があまり無い。
みんなそれぞれ、緩やかにやりとりがある。
だからこそ、塾生みんなが過ごしやすい空気ができている。
何より、私はこのような排他的な雰囲気を極度に嫌う。
そのような雰囲気をつくるというのは、人間的に未成熟であることの証だと思うからだ。(実際に起きたことはないが、仮に勉強の得意な子たちや通塾歴の長い子たちが、入ってきたばかりの子に対して大きな顔をしようものなら、私は厳しくたしなめるだろう。)
おそらくだが、みんなはじめて塾に来たときに、温かく迎えてくれたことをなんとなく覚えているのだろう。
そして、それが心地よいものだったのだと思う。
だからこそ、自分よりあとから入ってきた子たちに対しても同じように接してくれているのだと思う。
宿題は少なくはないと思うが、一方で大量に出すということはもちろんない。
指導者の安易な考えで大量に出すと、生徒たちは必ず雑なやり方になるからだ。
できるようになることが目的ではなく、終わらせること、ただこなすことが目的になってしまうのはありがちなことだ。
マルつけの仕方が適当になったり、答えを見ながら(写しながら)やったりしていては、意味がないどころか間違った習慣を身につけることになってしまう。
また、中学生も色々と忙しい訳で、部活動や習い事との両立をしながら塾の宿題をやらなければならない状況にある子がほとんどだ。
そういったことにも配慮して、「計画的に取り組めば無理なくやれる量」の宿題を出している。
ただし、物事を身につけるために反復練習をしたり、いろいろなパターンに触れたりすることが大切なのは間違いない。
だから、宿題の実施状況や理解度を確認し(ノートチェック・小テスト)、生徒たちの勉強の質を確認しながら、少しずつ分量を増やしている。
また普段より多めに宿題を出す際は、その意図や注意点を伝え、生徒たちに少しでも納得して取り組んでもらえるように心がけている。
欠席した場合は、授業の中で扱ったプリントやノートのコピーを渡す、あるいは集団授業以外の時間で補習を行うことで、次の授業に向けての準備ができるようにしている(完全な振替対応はしていない)。
授業というのは、その場に赴き、その場にいて学ぶことで、最大の学習効果を発揮する。
生徒本人にも、またご家庭にも負担はかかると思うが、なるべく欠席することなく、日々の授業に臨んでもらいたいと考えている(保護者の皆様、いつもご通塾を支えてくださりありがとうございます。また塾生の皆さんも、いつも頑張って通ってくれてありがとうございます)。
なお、下記の条件を両方満たす場合にはオンライン(Zoom)対応をしております(中学生以上)のでご安心ください。
①御家族がインフルエンザやコロナウイルス等に感染し、本人の登塾が難しいこと
②本人は心身ともに至って健康であること


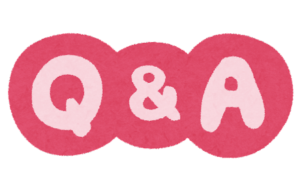
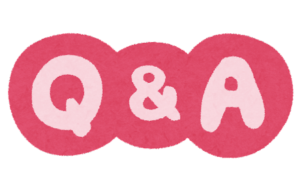
この記事が気に入ったら
フォローしてね!
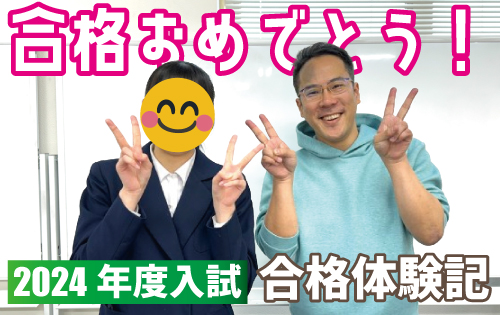
私がunitに入ったのは小学6年生の終わり頃でした。塾に入った頃は勉強の習慣もついておらず、テスト前だけ自習へ行くという生活を送っていました。そんな中、私が変わるきっかけとなった出来事がありました。
あるとき、塾へ通わなくなった時期がありました。なぜ通わなくなってしまったのかは、今の自分には正直分かりません。しかし、そのときに両親や先生方が私に寄り添って考えてくれました。そうしてくださったことで、私は勉強について考え直し、通塾を再開することができました。この出来事を通じて、自習に行く回数も増えました。そのとき、先生方が私の勉強をより助けてくださったことが私の大きな力になりました。
(中略)
また私は入試の1ヵ月前まで志望校をどうするか悩んでいました。私の第一志望の高校は決して倍率が低い高校ではありませんでした。私は自信が持てず、他の高校に変えようか悩んでいることを福永先生に相談しました。福永先生は私の考えを尊重した上で、私を信じてくれました。そのことが私の自信につながり、最後の1ヵ月も自分の勉強にしっかりと向き合い、勉強に集中することができました。そして、第一志望の高校に合格することができました。本当に嬉しかったです。
私はunitに入って勉強以外の大切なこともたくさん学びました。もしあのときunitを辞めていたら、今の自分はないと思います。勉強に対して前向きになり、自信を持つことができるようになったのは先生方のおかげです。先生、本当にありがとうございました。高校でも、もっともっと頑張ります。
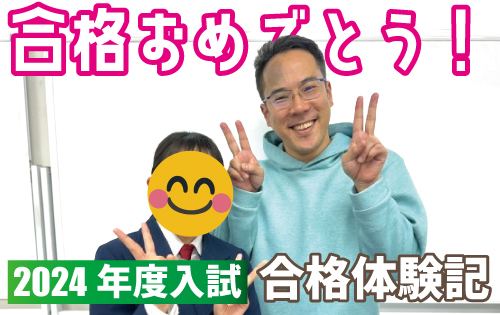
私がunitに入ったのは中学3年生の7月でした。だんだんと周りが受験勉強に本腰を入れる中、私は勉強に対する悩みがつきないでいました。 「なかなか結果が出ない」「勉強の仕方が分からない」と焦っていた私に母がunitを勧めてくれました。塾と聞くと「勉強ばかりで怖そう」というイメージがありましたが、そのイメージは体験のときから覆されました。優しくてコーモア溢れる先生方。勉強熱心な仲間、そしてあたたかい雰囲気に惹かれunitに入ることを決めました。
しかし、最初から順調という訳にはいきませんでした。今までずっと自分のペースで勉強してきた私にとって、塾のペースで仲間と勉強することは難しいことでもありました。慣れない環境の中、吹奏楽部の活動も続いていたため、宿題も日に日にできなくなっていきました。そのうちに申し訳なさと自分に対する嫌悪感が体調にも出るようになり、授業を休んでしまうこともありました。毎日、毎日負のループにはまっていくような感覚でした。この負のループから抜け出させてくれたのが先生方でした。どんなときでも私を責めたりせずに受け止めてくれました。勉強のサポートや体調面の相談まで本当にいろいろなところまで支えてくれました。正直、最初は驚きました。「塾の先生なのに自分のためにここまでしてくれるのか」と。 もちろんこの時期だけではなく、日頃から手厚いサポートをしてくださいました。そのおかげで私は変わることができました。
まずは勉強に対する姿勢です。塾に入るまでの私は苦手と向き合うことが嫌いでした。特に理科と社会は北辰テストでも足を引っぱっていました。それを見かねた福永先生が理科と社会の勉強の仕方を教えてくださいました。最初の頃は分からないことも多く、何度も苦手教科から逃げようとしていました。その度に福永先生がいいタイミングで「分からないところはない?」「質問ある?」と声をかけてくださったんです(心が読めるんでしょうか……)。私はなんとか逃げ出さずに、自分から分からないところを質問できるようになりました。塾に入りたての頃には「分からない」と伝えることが怖かったのですが、先生方は「いい質問だね」と心よく引き受けてくれたので安心して質問することができました。
勉強だけではなく人としても成長できました。もともと不安や緊張などの気持ちが体調に出やすかった私は、この体質に何度も悩まされました。体調が悪いと普段は出来ることも出来なくなります。私が何より心配していたのは受験当日でした。私立の受験が近づくにつれ、腹痛が悪化し始めました。それを見た福永先生と生田目先生は何度も緊張に対する向き合い方を話してくださったのです。その中で驚いたのは「緊張は戦う準備が出来ている合図」「集中モードに入っている」とプラスにとらえていたことです。その話を聞いてからは自然と腹痛が治っていき、当日には自分でも驚くほどリラックスしていました。あんなにも悩んでいたものから解放されたことは、安心や自信につながりました。
最終的に、私は第一志望に合格というかたちで受験を終えることができました。unitに出会ってなければ、正直このような結果にはならないで終わっていたと思います(もう少し早く出会いたかった気もしますが)。ここでは書ききれないくらい、先生方に支えていただきました。本当に本当に感謝でいっぱいです。unitに入ることができてよかったと心から思います。
unit、大好きです。

私がunitに入ったのは中2の6月頃でした。今では考えられませんが、当時は宿題をロクにやらず、よく怒られていました。ほとんど勉強していなかった私にスイッチが入ったのは、中3の夏期講習でした。この時期に、毎日勉強せざるを得ない状況に追い込まれ、勉強する習慣がつきました。最初は大変でしたが、この夏期講習があったからこそ成績が上がり、より高い志望校を受けようと思うことができました。
(中略)
受験が近づいてきた時期、あることが理由で自分がなぜ頑張っているのかが分からなくなり、悩んだこともありました。しかし、福永先生が悩みを真剣に聞いてくださり、塾の仲間が相談相手になってくれたことで、これを乗り越えてラストスパートをかけることができました。合格することができた一番の理由は、先生方の熱心なサポート、ときに友人、ときにライバルとなってくれた塾の仲間、そして家族など、身の周りの人たちの存在があったからだと思います。この場を借りて、感謝を伝えたいです。
後輩の皆さんの努力の積み重ねが実り、桜が咲くことを祈っています。

私は塾に入る前後で、比べものにならないくらい勉強への向き合い方が変わりました。最初の頃は「この志望校に行けたら奇跡だ」と思っていましたが、unitで頑張って、選べる高校の幅が本当に広がりました。一年間の受験勉強を通じて勉強を好きになれたし、自分自身を強くすることができたと思います。
また周りの人がいかに自分を支えてくれているかが分かるようになりました。合格することが出来たのは親、塾の先生、そして塾の仲間たちやライバルの存在があったからだと思います。
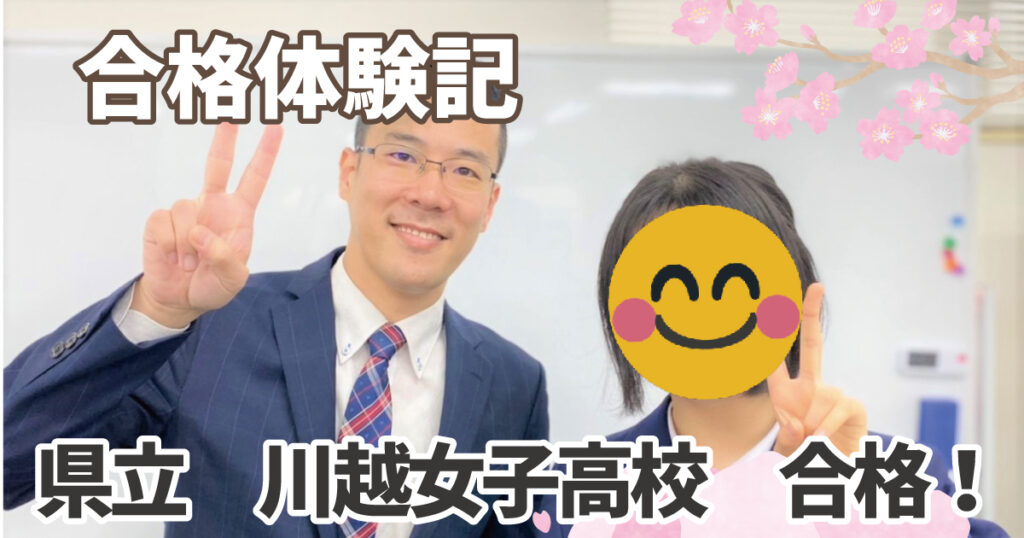
私は中学1年生の秋頃から数学が苦手になりました。体験授業のときに福永先生がとても分かりやすく数学を教えてくださり、苦手を克服できると思いました。
unitはとても質問をしやすい環境です。授業時間内に質問できる時間があり、分からない部分を放置することはなくなりました。また質問した際に演習不足だと分かったときには、先生が演習用のプリントを用意してくださいました。そのおかげで、自分の理解不足の単元はほとんどなくなりました。そして何より数学の面白さを知りました。今では数学が一番好きな教科です。

私が進学塾unitに入塾したのは、中学2年生の冬でした。それまでの私は毎日の勉強習慣が全く身についておらず、高校受験に向けた学習もしていませんでした。しかし、毎日塾に行って自習をするようになったことで勉強量が増え、成績も大きく伸ばすことができました。
私が合格できたのは、福永先生の指導と勉強を毎日続けてきたことのおかげだと思います。またunitに入ったことで学習面だけでなく、色々な部分を成長させることができました。unitに入って本当に良かったと思います。

僕は中学1年生のときに入塾しました。はじめはbe動詞と一般動詞の違いすらも理解できずに入塾しました。先生たちの教え方や進め方がとても上手だったり、面白いゴロを教えてくれたりと、本当に分かりやすかったのを覚えています。英語は少し得意になり、読むのが楽しくなりました。
また、生田目先生の国語の授業では論理的思考を用いた授業をしていて、言葉について興味や関心を持つことができるようになりました。このことで文章が読みやすくなり、分からない言葉はすぐ調べるという習慣も身につきました。(中略)
入塾して最初の定期テストがやってきました。ここで僕は以前よりも集中して取り組むことができるように成長していました。しかし、テストは自分が思ったような点数が取れず、少し勉強に対してやる気をなくしてしまいました。そのとき、塾長の福永先生が励ます言葉をかけてくれました。そのおかげでだんだんとやる気を取り戻ることができました。
受験生になって、勉強量も増えました。最初は勉強量の多さに理解が追いついていかず、辛い日々もありましたが、周りの人もがんばっているのだと思うと、気を抜いてはいけないと思い、頑張りました。その後、定期テストの点数も最初よりも合計で100点以上上げることができたので良かったです。受験は終わったけれど、その後が大事だと思うので、これからも勉強を頑張っていきたいです。本当に通って良かったと思います。
2年間、ありがとうございました。

私は、受験生になるのがすごく不安でした。周りのみんなについていけるかどうか、毎日長時間勉強できるのか……など、受験生になるのが本当に怖かったです。だけど、先生方が私に優しく寄り添ってくださいました。そのおかげで、私のペースで少しずつ少しずつ成長することができたと思います。
夏期講習に入って本格的に受験勉強が始まってから、私は各教科の具体的な目標を立てました。それを自分の目に入りやすい所に置いて、塾が終わってからも自宅で勉強していました。すぐに結果に表われるとは限らないと先生たちから聞いていたので、粘り強く勉強を続けました。その結果、3.4か月後に一気に伸びました。そのとき飛び上がって喜んだのを覚えています。
そして、英検の準2級も取得することができました。やればやるほど結果に表われていくのを実感して、勉強することがとても楽しくなりました。
もちろん、ずっと上手くいっていた訳ではなく、落ち込んでしまうこともあったけれど、塾にいると、優しい先生や友達に囲まれて、頑張ることができました。毎日毎日、全力で指導して下さった先生方には、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

私がunitに入塾したのは、中学2年生の5月頃でした。当時は定期テスト前にだらだらと勉強するだけで、ほとんど勉強をしていませんでした。私の中で勉強は、めんどうなもの、つまらないものとなっていました。
しかし、unitに入り授業を受けて、初めて勉強を楽しいと思いました。それは授業が楽しかったからです。授業では、ただ公式を教えるのではなく、公式が成り立つまでの途中式まで解説してくれたり、何が原図でその出来事が起きたのか、どんな影響を及ぼしたかまで教えてくれたりします。このことで覚えやすくなっただけでなく、自分で勉強するときに、自ら気になることをすぐに調べる癖がつきました。
また先生方が、フレンドリーに接してくれるので、調べてもわからないことや疑問に思ったことの質問がしやすかったです。
私は塾に入る前からずっと英語が苦手でした。2年生の終わり頃、このままではまずいと感じ、塾長である福永先生に1年生の範囲から教えてほしいとお願いしました。福永先生は快く引き受けてくれました。授業が終わった後の時間に基酸中の基礎からやり直してくれました。このことをきっかけに、英語が少しずつ出来るようになり、英語を勉強することが楽しいと思うようになりました。ずっと苦手で避けてきた英語の勉強が楽しいと思うようになったことに自分でも驚いています。
受験を終え、第一志望校に合格できた今、改めてunitに入って良だったと思います。きっとunitに入らなかったら、ずっとだらだらとした勉強を続け、目指せる学校の幅も狭まっていたと思います。良い勉強の仕方や、勉強以外の礼儀などもわからなかっただろうと感じています。
一生懸命に取り組む仲間や私たちに親身になってくれる先生方に囲まれ勉強ができたこと、毎日大笑いしながら授業を受けられたことに感謝しています。素晴らしい仲間とともに、unitで過ごした日々は私にとって大切な思い出です。たくさんのことを教えてくれた先生方、本当にありがとうございました。

私がunitに入塾したのは、1年生の1学期中間テストの勉強会のときでした。それまでの勉強は学校の宿題だけで、勉強は好きではありませんでした。普段勉強していない私が勉強会に参加したため、耐えきれずに夜の部を休んだこともありました。
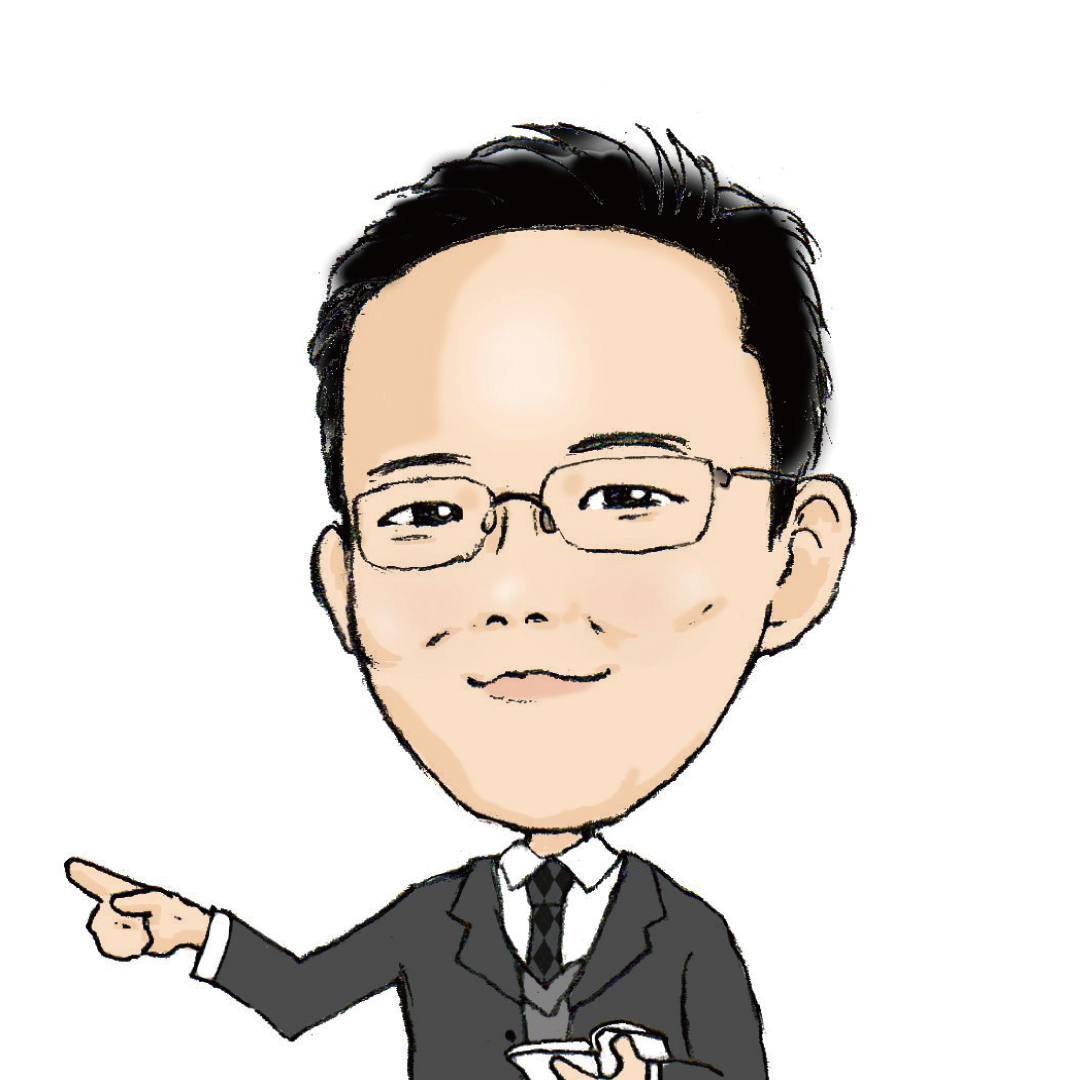
←懐かしいですね。そんな時期もありましたね(^-^)
しかし、受験生を経験した今では余裕です。当たり前にこなせるようになりました。unitの授業はとにかく楽しかったです。塾長のつまらないギャグ。副塾長の色々な話。
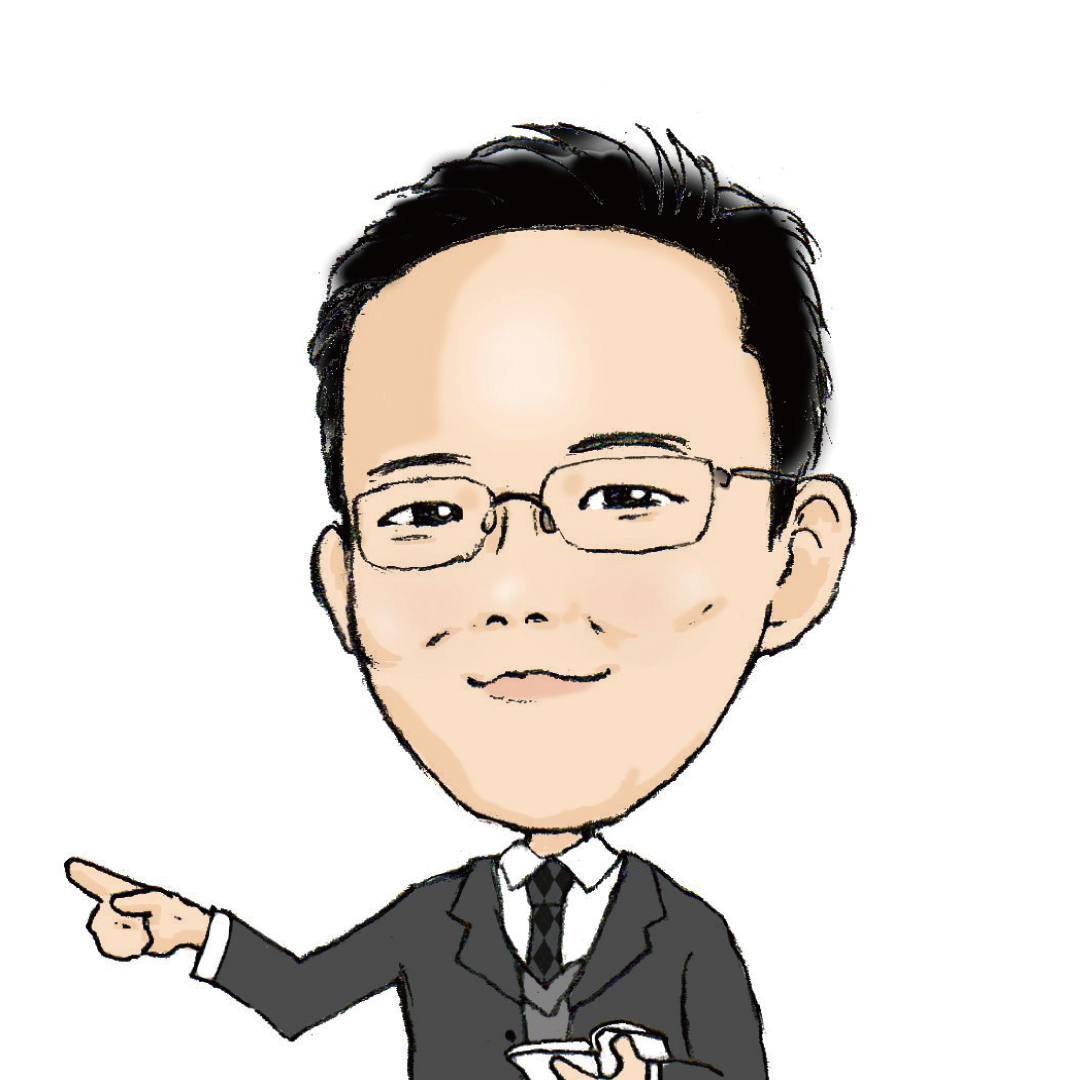
あなたがクラスで一番笑っていましたが!!??
それに対するみんなの反応が面白くて、unitが私にとってのsecond homeになりました。授業の前の出席確認がunit流なのも楽しいポイントです。「好きな芸能人」や「好きな曲」など毎回お題が変わることでみんなのことを知れたので、仲間意識が強まったと感じています。
しかし勉強はハードでした。小テストの量、宿題の量、テスト勉強会の長さ、授業のコマ数が多い、塾長が意外と怖いなどなど……。
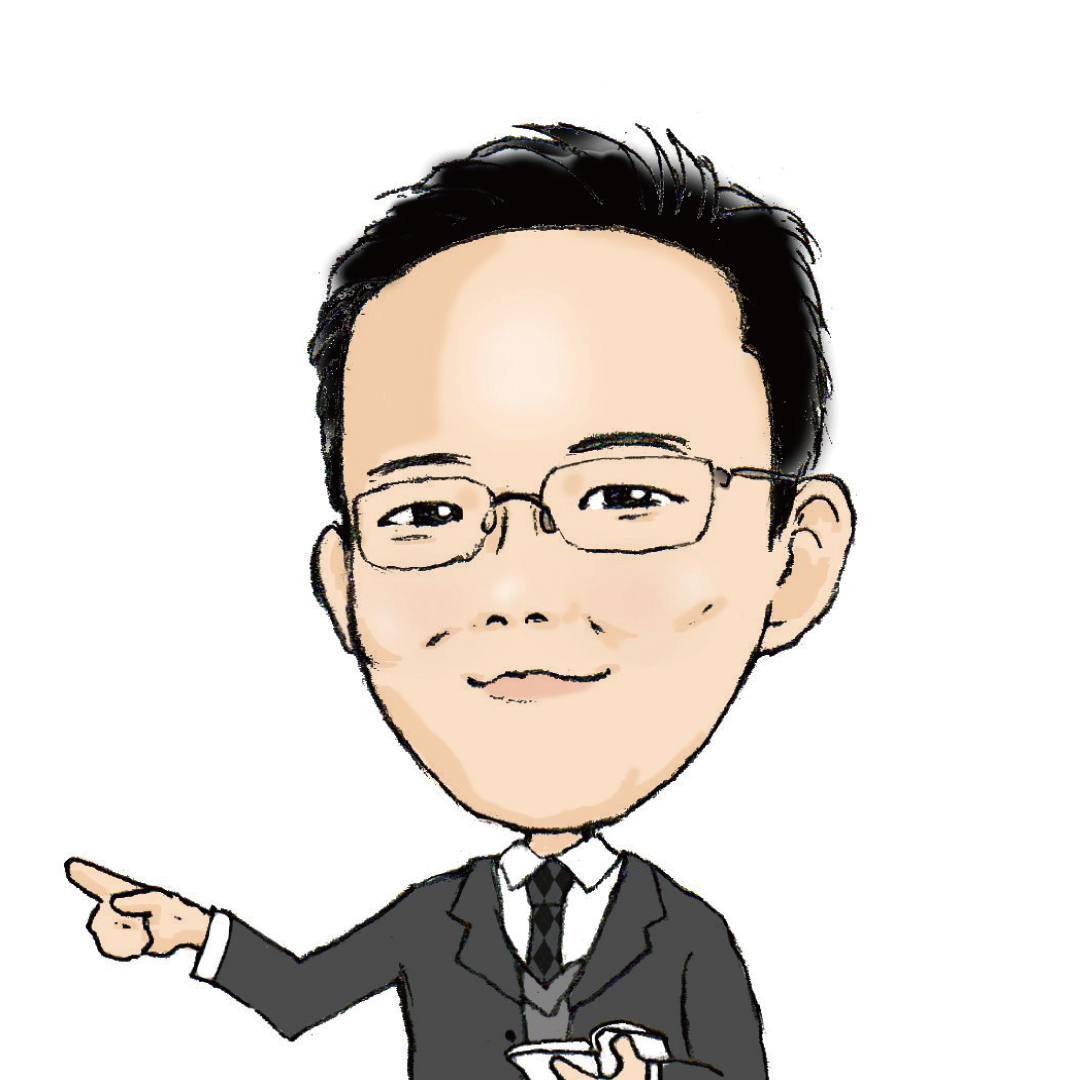
受験は真剣勝負ですから……。でもゴメン汗
勉強が思うように出来ない自分に対して泣いたときもありました。分からないことが多いから時間が足りなくて、睡眠時間を削らざるを得ないときもありました。今となってはすべて良い思い出です。
unitで学んだことは勉強だけではありません。お礼や挨拶などの礼儀も学びました。unitに通っていなかったら、きっと志望校にも合格できずにいたと思います。1年生のときに勉強会に誘ってくれた福永先生には感謝しています。unitのおかげで充実した3年間になりました。

僕は中学二年生の春に進学塾unitに入塾しました。まず僕が以前に通っていた塾との違いに驚かされました。具体的には積極的に参加できる授業の雰囲気と授業の質です。
入塾する前は考える力があまり身についておらず理科も苦手でしたが、入塾してからは授業でも宿題でも考えることが常に必要だったので、考える力が身につき、理科の成績もとても伸びました。また頭をそんなに使わないと思っていた社会が、本当はとても頭を使うということに気づきました。日頃の授業で物事のつながりや因果関係教わり、記述問題も解きやすくなりました。
また国語では論理的思考力が少し身についてきたと思います。はじめは、国語はすべて勘と運で解くものだと思っていましたが、授業を通して、色々な関係を意識して読むことができるようになりました。(中略)
このように、進学塾unitでは、たくさんの気づきがありました。気づかせてくれたのは先生方です。先生、ありがとうございました。

私がunitに入ったのは中学2年生の3月からでした。塾に入ったら「勉強」「勉強」という毎日になるのがとても嫌で、塾に入るのもずっと拒んでいました。普段も宿題とテスト勉強など最低限のことしかしてきませんでした。しかし、塾に入ってみると私が想像していた塾とはまったく違いました。毎日楽しく授業を受けることができて、先生方に気軽に質問できました。自然と勉強をする環境をつくっていくことができました。
私が行きたいと思う高校が決まったのは4月頃でした。福永先生に紹介していただき、最初はあまり聞いたことのない高校だったのですが、調べていくうちに段々と魅力にはまっていき、志望校になりました。明確な目標ができたため、それからさらに勉強をしていくようになり、自習室にも毎日行くようになりました。
成績の面では少しずつ学校のテストの点数は上がっていき、通知表も塾に通う前から遥かに高くなっていきました。ですが北辰テストの偏差値は努力に比例しないことが多く、夏期講習明けの北辰も成績が下がる一方でモチベーションが段々と下がっていきました。それでも諦めず「塾に行けば勉強する環境がある」と思い、塾に通い続けました。すると12月頃に急に北辰の成績も上がりました。
私の志望校は小論文と面接がありました。先生方に相談すると快く引き受けて下さり、生田目先生には小論文の対策、福永先生には面接の対策をしていただきました。だんだん入試への不安を消していくことができました。今思うと、気軽に何でも引き受けてくださったからこそ、様々なことができるようになったのだと思います。
推薦入試では入試当日に自分の今までの力が発揮できずに落ち込んでしまい、福永先生にたくさん相談をしました。落ち込む私に対しても福永先生はずっと前向きでいてくれて、私が頑張れるように後押しをしてくれました。そのため私は切り替えを早くすることができ、推薦入試は残念な結果に終わってしまいましたが、一般入試では合格という結果が残せました。
unitに入ったことは、勉強だけでなく、私が将来に向けて努力できる人間になる良い機会になったと思っています。授業も楽しく、本当に充実した1年でした。塾がこんなに楽しくなかったら一年間こんなに努力できなかったと思います。先生方、同級生のみんなに本当に感謝しかありません。本当にありがとうごいました。

塾の授業は周りの雰囲気も良く、なにより先生方が明るく面白いので、苦手な勉強も楽しく学ぶことができました。
また塾では小テストや再テストがあります。
テストで間違えた部分を復習したり、分からない部分を先生に質問したりしながら、ちゃんと理解することができました。
塾に入る前は勉強が苦手であまり勉強をしていませんでした。
しかし塾に通い始めてから自習に行くようになり、以前よりも格段に勉強する時間が増えました。
勉強時間が増えたことで、最初は大変に感じましたが、塾で毎日勉強していくうちに、当たり前になっていきました。
とてもハードでしたが、頑張って乗り越えることができました。
(中略)
受験当日は緊張と不安がありましたが、福永先生がくれた手紙に書いてあるアドバイスを読み、不安が安らぎ、落ち着いてテストに臨むことができました。
僕はこの塾に入り、勉強だけでなくさまざまなことを学ぶことができました。
合格することができたのは、ときに優しく、ときに厳しい先生方のおかげだと思います。

私は毎日、片道1時間かけてunitに通っていました。
unitでは授業中に間違えても良い雰囲気、いつでも質問しやすい雰囲気が醸成されています。
また生徒たちみんなが授業と休み時間の切り替えを早くできて、全員が勉強に集中できる空間となっています。
自発的に勉強を始める。
休み時間は思いっきり休む。
そんな雰囲気があるunitで毎日勉強したら成績が上がるに決まっています!
unitは決してラクな塾ではありません。
しかし先生方が楽しく、丁寧な指導を毎日してくださいます。
私は先生方と楽しく、ときには厳しく勉強することで、志望校に合格することができました。
また勉強面だけでなく、人間的にも大きく成長することができたと思います。
私はunitで勉強できて良かったです!

私が進学塾unitに入塾したのは、中学1年生の夏ごろでした。
入塾する前は定期テスト前しか勉強しておらず、普段はほとんど勉強していませんでした。
勉強の習慣化が大切と先生に教わったので平日は毎日自習に行くようになりました。
「家でのんびりしたいな〜」という怠け心が出てくるタイミングで塾に新しいアイテム(漫画や小説)が投下されるので、それに釣られてまた自習に行くという、、。
もしかしたら、先生が私が自習に行きたいと思うようにしてくれていたのかな?と思っています。
また、幼稚園の頃から英会話教室に通っていたので、英語は1学年上の授業に参加していました。
また数学も中学2年生の時から1学年上の授業にも参加していました。
今考えると、この先取りが受験生になった時に大きなものになったのだと思います。
いざ受験生になると、1、2年生の先取りのおかげで進路選択の幅が増え、偏差値だけにとらわれず志望校を考えることができました。
また、難関コースを受講していて、発展的な内容の英数国を勉強することが出来たので、学校選択問題の対策になったと思います。
私が受験生としての自覚を持ったのは中学3年生の秋ぐらいだと思います。
それまではなかなか実感が湧かず、計画性も無く勉強をしていました。
そして気づけば受験の天王山と呼ばれる夏休みが終わり、滑り止めの私立高校を決めなければならない時期になりました。
そして、北辰テストの結果が進路に大きな影響を及ぼす可能性があるこの時期に、私の英語の偏差値は伸び悩んでいました。
原因は、英語を文法に則って解いておらず、感覚(フィーリング)で解く癖が抜けないことでした。
これが直前の2月まで大きな課題となりました。
1月から、塾の先生から借りた長文のテキストを毎日1つずつ解き、きちんと文法に則って論理的に解けるように努力しました。
その甲斐あってか、最初は低かった県立過去問の英語の点数もだんだんと上がってきて自信がついてきました。
本番は特に緊張もせず、今までの勉強の成果が発揮できたと思います。
そして、無事第一志望校に合格することが出来ました。

僕が進学塾unitに入塾したのは、3年生に進級する直前でした。
きっかけは、友だちに体験授業に誘われたことでした。
当時の僕は塾に入ることなんて考えていませんでしたが、授業を体験してみるととても楽しく分かりやすい授業だと感じました。
「ここなら楽しみながら自分の学力を上げることができる。」
そう思い、入塾を決断しました。
入塾したての頃は塾の宿題に追われて、効率よく取り組むことができませんでした。
しかし先生が親身になって勉強のやり方を教えてくれました。
そのお陰で勉強を習慣化することができました。
成績が上がったときはとても嬉しかったです。
ところで、僕はもともと英語が苦手でした。
とくに中2で不定詞を学習したところで英語が苦手になりました。
しかし塾で不定詞の復習をしてもらい、しっかりと理解することができました。
また夏期講習では英語の長文テストで「100点を取る!」という気持ちで勉強しました。
するといつの間にか英語が得意教科の一つになっていました。
苦手意識がなくなっただけでなく、英語が楽しく感じられるようになったのは塾のおかげだと思います。
(中略)
一年間の受験勉強を通じて、受験の厳しさ、そして勉強の楽しさが分かりました。
合格することができたのは、親、塾の先生、友だち、ライバルの存在があったからだと思います。
進学塾unitに入って、本当に良かったです。

受験を終えて、unitに入ってからの日々を振り返ってみると、本当に密度の濃い充実した日々だったと感じています。
私は2年生の6月頃に入塾しました。
当時は勉強の習慣もついておらず、怠惰な生活を送っていて、とても学業を本分とする学生のあるべき姿とは言えない状況だったと思います。
しかしこんな私でも、なりたい自分へ近づくことができました。
unitに入ってから、私にとって転機になった出来事が二つあります。
一つ目は塾長である福永先生から数学の問題への取り組み方について指導を受けたことです。
一対一での演習において、難しい問題でよく手が止まっていました。
すると福永先生が
「基本動作(座標や比を書き込むことなど)を、息を吸うかのごとく自然に出来るようにしよう。手を動かすことで気づけることもたくさんあるんだよ。」
「試験本番では時間制限のあるなかで良いパフォーマンスを発揮しないといけない。だから、普段の演習の中でも素早く手を動かせるようにして、制限時間を意識しないといけないよ。」
と教えてくださいました。
このやりとりを通じて私は「苦手教科である数学だから出来なくても仕方ない」と、考えることをやめてしまっていたことに気づきました。
二つ目は、私の国語の実力を福永先生が見いだしてくださり、そして私の力を信じてくれたことです。
今の私にとって、国語が一番の得意教科であり好きな教科ですが、入塾した当時は意識したことが一度もありませんでした。
そのような中で福永先生が私の国語の力について褒めてくださったことで、国語に対する意識が変わっていったのだと思っています。
3年生になってからは生田目先生からのご指導を受けて、より論理的に考えることができるようになり、試験本番でも一番満足のいく結果を出すことができました。
ずっと信じ続けてくれて本当に感謝しています。(中略)
高校受験において自分自身で決断しなければならない場面もたくさんありました。
その最たるものは志望校の決定です。
高校に入ってからのことや私の体調面も考えた上で、どうするかとても悩みました。(中略)
自分なりに悩み、決断したという経験はこれからの人生に活かすことができますし、悩み迷っている人に寄り添うことができる人間へと成長する糧となりました。(中略)
unitで素晴らしい仲間とともに学び、笑い合えたことはかけがえのない大切な思い出です。
この一年間を自信に変えて、新たなスタートを切りたいと思います。
一年間、ありがとうございました。